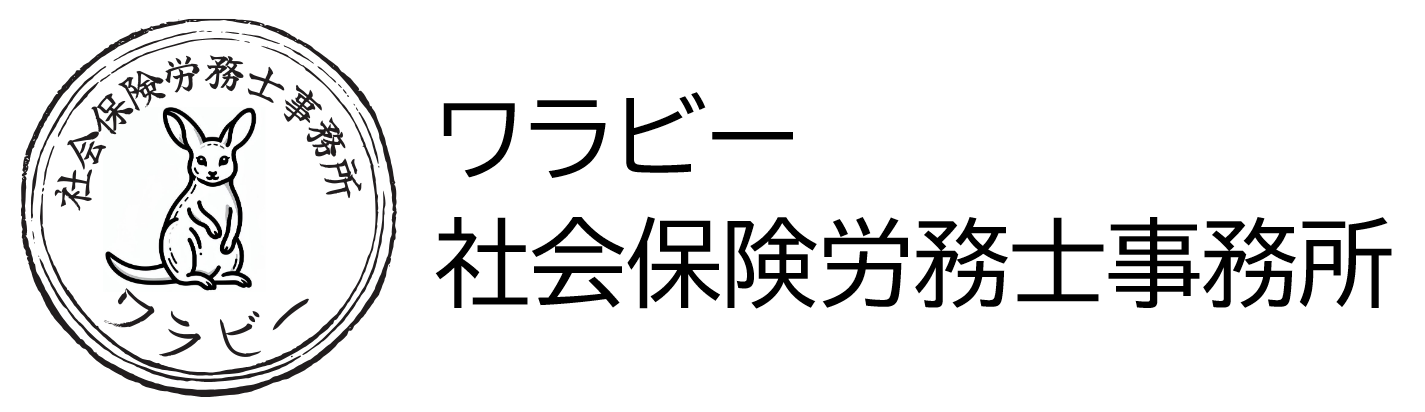自衛隊ヘリパイロットが語る“構え”と“備え”──企業経営にも通じるリーダーシップの極意
私は、自衛隊でヘリコプターパイロットとして長年訓練を積んできた経験を活かし、現在は社会保険労務士として中小企業や個人事業主の皆さまをサポートしています。自衛隊におけるヘリコプター運用は、いつどんなトラブルが発生するか分からない、いわば“極限の現場”です。天候の急変、機材の不具合、人員のコンディションなど、常に複数のリスクと隣り合わせで任務を遂行してきました。そんな環境で身にしみて感じたのが、「構え」と「備え」の大切さです。百戦錬磨の経営者の皆さまに改めてお伝えするまでもないかもしれませんが、私はこの二つが経営にも驚くほど通じると確信しております。以下では、具体的なエピソードを交えながら、このエッセンスをご紹介したいと思います。
■ 構え:リーダーとしてのマインドセット
まずは「構え」です。これはリーダーとしてのマインドセットを意味します。ヘリコプターを運用して任務を行う現場では、ちょっとした天候の変化が大事故につながる可能性があります。ある日の訓練では、空が急速に曇りはじめ、わずか10分ほどで100m先も見えないような大雨に見舞われました。離着陸に影響が出るほどの豪雨のうえ、遠くでは稲光が走り出す始末です。
こうした状況で、もし指揮官が焦りや不安を表に出してしまうと、操縦士や幕僚、整備員などチーム全体が一気に動揺し、「このまま飛び続けて本当に大丈夫なのか」という疑念が広がります。その結果、大雨の中で視界不良のまま飛行場に着陸しようとして失敗したり、不用意に雷雲に接近して雷を受けたりするなどの思わぬ事故を招きかねません。
そこで、指揮官である私が徹底したのは、たとえ内心で不安を感じていても決して顔に出さないことでした。人間ですからリスクを感じれば不安になるのは当然です。しかし、部下はリーダーの一挙手一投足を注視しています。ほんの小さな動揺でも「指揮官が怖がっている。これは相当危険なのではないか」と、部下たちの不安が一気に広まってしまうのです。そのためこそ、状況が悪化したときには、冷静に天候情報を収集させたり、飛行中の航空機の燃料残量を確認させて残りの飛行可能時間を共有したりなど、落ち着いた声色で対応策を示し、部下に安心感を与えることが求められます。こうした“構え”がないと組織はすぐに乱れ、最悪の場合は大きな事故にもつながりかねません。
経営においても同様です。もし社長や役員クラスの方が不安や苛立ちを露わにすると、社員は必ずそれを察知します。たとえば、新製品の発売日程が遅れそうだとか、大口顧客から重大なクレームが入るなどの問題が起きたときに、トップが取り乱してしまうと組織全体の不安が一気に高まり、適切な判断ができなくなります。しかし、社長が「大丈夫だ、今から対策を立てよう」と落ち着いて声をかけるだけでも、社員は「社長に任せておけば大丈夫だ」と安心します。内心では冷や汗ものだったとしても、そこにこそリーダーとしての強い「構え」が表れるのだと考えています。
■ 備え:不測の事態への具体的な準備
次に「備え」です。ヘリコプターで各種任務を行う際には、万が一のトラブルに備えて常に複数の緊急着陸地点を把握し、燃料残量や通信手段を二重三重にチェックしていました。夜間飛行訓練では、飛行前点検で航空機の各種灯火や照明灯を入念に確認すると同時に、手持ちの照明やハンディGPSを準備します。さらに乗員全員で故障時の手順を事前共有し、同じ時間帯に飛行するほかの航空機クルーとも互いの飛行経路を確認し合うことで、事故を防ぐ体制を整えます。エンジン故障を想定したオートローテーション着陸訓練やシングルエンジン着陸訓練も日常的に行い、天候が急変した場合にどの飛行場や河川敷を使用できるか、緊急着陸後にはどのように連絡を取り合うか、整備員を現地へ派遣するにはどうすれば良いか——こうした一連の流れをすベての関係者で共有しておくことで、いざというときにも慌てず対処ができるのです。
ビジネスの世界も、VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代に突入し、自然災害やパンデミックなど、それまで想定しなかったリスクが次々と起こり得るようになりました。だからこそ事業継続計画(BCP)の策定や資金繰りのシミュレーション、さらにはサプライチェーン断絶時の代替ルート確保など、あらゆる可能性を検討しておく必要があります。そうした「備え」を怠れば、いざというときに大きな損失を被るのは目に見えています。たとえば、ある中小企業ではサイバー攻撃で主要システムがダウンしてしまい、バックアップを定期的に取っていなかったために半年分のデータが復旧不能になったといいます。もし事前に対策や訓練を行っていれば、被害を最小限に抑えられたでしょう。
また、人材面でも「備え」は極めて重要です。キーパーソンが急病で入院したり、突然退職したりという可能性に備え、業務の属人化を避ける努力が必要です。管理職は業務をひとりで抱え込むのではなく、部下に仕事を任せ、交代しながらノウハウを共有することで、誰かが欠けても業務が滞らない仕組みをつくることが大切です。それを怠り、部長クラスの人材が急に退職してしまった結果、大きな顧客との案件が一時的にストップしてしまった企業もあります。長年、実業を営んできた方であれば、こうしたリスクがどこにでも潜んでいることは十分ご存じでしょう。
■ 終わりに
自衛隊での経験を振り返ると、組織の安定や成功を左右する要素として「構え」と「備え」の二つがいかに重要かを痛感します。想定外の事態が起きたときに、リーダーが冷静で落ち着いた態度を貫いて部下に安心感を与える「構え」がなければ、組織は混乱に陥るかもしれません。そして、その「構え」を支えるのが日頃の「備え」なのです。訓練やマニュアル整備を通じて万が一に備えておけば、想定外の出来事が起きても落ち着いて行動できます。これはそのまま企業経営にも当てはまる原理だと思います。
百戦錬磨の経営者の方々にとっては、既に実感済みの内容かもしれません。しかし、日々の業務に忙殺される中で、改めて組織の足元を見直す機会は減りがちでもあります。ぜひ、私が自衛隊の現場で学んだ教訓である「構え」と「備え」を今一度意識し、揺るぎないリーダーシップと万全の体制づくりを追求してみてください。何があっても舵を取り続けられるよう、本稿でご紹介した内容が少しでもお役に立てば幸いです。