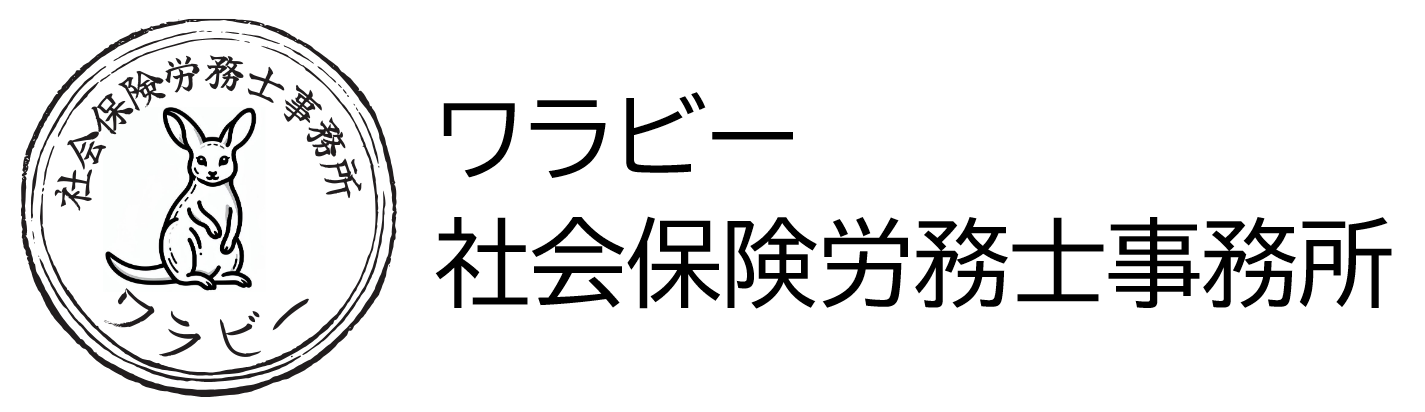リスクホメオスタシス対策の成功例について
リスクホメオスタシス対策は、「新たな安全装備や厳格なルールが導入されても、人間が油断してリスクレベルを元に戻してしまう」という心理傾向をどう防ぐかがテーマです。ここでは、その対策がうまく機能しているいくつかの成功例を挙げてみます。
成功例1:航空業界におけるCRM(Crew Resource Management)の導入
航空業界は最新の自動操縦システムや高度なアビオニクスが発達しており、パイロットが機械任せで油断してしまうリスクが常に存在します。そこで導入されたのが、クルー全員で互いの状況をチェックし合いコミュニケーションを密にする「CRM(Crew Resource Management)」です。たとえば副操縦士や客室乗務員も含め、全員が気になる点を即時に共有し、階級や役職の隔たりを超えて安全に対処する仕組みを徹底しました。これにより、「装備が優秀だから大丈夫」とパイロットが慢心するリスクを抑え、クルー全員で安全レベルを高く維持する効果が期待でき、実際に事故件数の低減に貢献しています。
成功例2:自動車の安全装備+啓発キャンペーン
自動車業界では、安全装備が充実すればするほどドライバーが「クルマが勝手にブレーキしてくれる」と過信しがちです。そこでメーカーや行政は、安全性能のアピールとともに「あくまで補助装置であり、ドライバーには常に注意が求められる」ことを強く訴えるキャンペーンを行いました。例えば、衝突被害軽減ブレーキが普及する際、「ブレーキは補助機能であり、ドライバーがブレーキ操作を怠れば事故は避けられない」といった警告を繰り返し表示するPR動画やSNS広告を展開。これによって「安全装備があるから安心」だけではなく、「正しい運転姿勢を保つ必要がある」と認識されやすくなり、大きな事故を減らす成果を上げています。
成功例3:工場現場での“見える化”+指差し呼称の再教育
製造業の工場では、センサーやアラームなどを導入して危険な工程を監視すると、作業員が「センサー任せ」で注意力を下げがちです。そのため、“見える化”によって「今どの工程が危険レベルにあるのか」を明示したり、作業ごとに「指差し呼称」のルールを再度徹底したりする取り組みを行っています。単にシステムの導入だけでなく、「作業員のリスク意識を高めるための教育を繰り返す」「なぜ指差し呼称が必要なのかを具体的な事故例まじえ理解してもらう」といった説明を徹底することで、「システムがあるから安全」ではなく「自分たちの行動が安全をつくる」というマインドが浸透し、ヒューマンエラー事故の発生を大きく抑制しています。
成功例4:長寿企業が“棚卸し”と背景共有を実施
古い慣習や複雑な手順が多く、皆が「なぜその手順が必要か」を分からず守っているだけという企業が、定期的に社内ルールを整理し直す活動を行っているケースがあります。もともとの失敗事例に遡り、「かつて大きな事故やミスを防ぐために導入された」という背景までくわしく共有すると、社員はルールの本質的な意味を再確認しやすくなります。こうした活動を継続している企業では、「つい形骸化しがちな手順」を社員が主体的に見直す文化が生まれ、「どうせルールだから仕方ない」と無意識に形だけ守るのではなく、自発的にリスクに備えようという意識が芽生え、事故や不祥事が少なくなる傾向があります。
これらの成功例で共通しているのは、「新しい安全策やルールを導入するだけ」ではなく、「自分ごととして危険を認識させる教育・啓発」をきちんと行い続けている点です。装備やシステムへの依存だけに寄りかからないよう、背景の共有や定期的な棚卸し、コミュニケーションの強化が欠かせません。こうしたアプローチがあってこそ、リスクホメオスタシスをできる限り抑え、安全を維持することが可能になります。