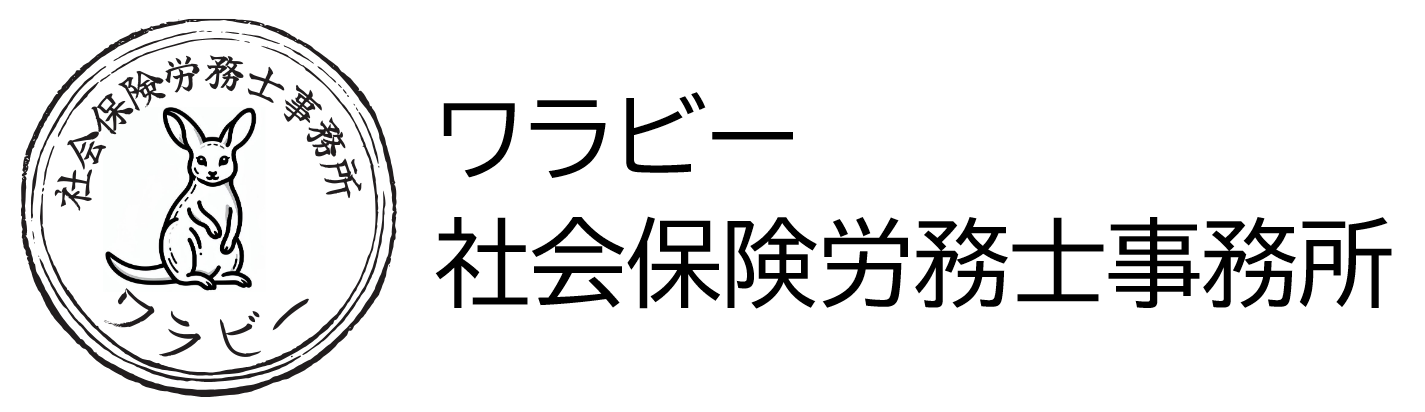そのリスク、見過ごせますか?
労働災害は、今や物理的な事故だけではありません。過労やメンタル不調によるリスクが急増し、企業の安全配慮義務はかつてなく広範になっています。労災認定後の高額な追加賠償事例は、他人事ではないのです。
1億円超
精神障害・過労死関連での賠償額事例
46.3%増
社会福祉施設での死傷者数(2017年比)
No. 1
事故の型で最も多い「転倒」
このレポートは、最新のデータと裁判例に基づき、貴社が直面する安全衛生リスクを可視化し、具体的な対策を考えるための一助となるものです。
変化するリスクの潮流
従来の「墜落・転落」といった物理的災害に加え、「メンタルヘルス不調」や「過労死」といった新たなリスクが顕在化。企業の対応力が問われています。
災害種類別 賠償事例の傾向
下のボタンで関心のある災害の種類を選択すると、関連する賠償額の傾向(年平均)と代表的な義務違反の内容が表示されます。
代表的な安全配慮義務違反
- 安全設備・防護措置の不備
- 安全教育・作業手順の不徹底
- 長時間労働・過重業務の放置
- ハラスメント・健康管理体制の不備
- テレワーク等の新たな働き方への対応不足
経営を揺るがす、高額賠償リスク
労災保険だけではカバーできない損害賠償は、企業の財務に深刻な影響を与えます。過去の事例から、その実態を学びましょう。
労災保険で補償されない費用
万が一の際、労災保険とは別に、企業が負担する可能性のある主な費用です。特に慰謝料は高額になる傾向があります。
慰謝料(後遺障害・死亡)
休業損害の一部(労災支給60%に対する差額40%分)
逸失利益の一部
弁護士費用などの訴訟対応コスト
賠償額は高額化傾向
特に精神障害や過労死に関連する事案では、賠償額が1億円を超えるケースも散見され、年々高額化する傾向にあります。
安全配慮義務違反による追加賠償事例
業種や災害の種類でフィルタリングし、貴社に関連の深い事例をご確認ください。各カードをクリックすると詳細が表示されます。
貴社の備えは万全ですか?
安全配慮義務は、法律で定められた最低限の基準を守るだけでは不十分です。今、企業にはより積極的で包括的な取り組みが求められています。
安全衛生管理体制の構築
形骸化した規程の見直しや、安全衛生委員会の活性化、現場のリスクアセスメントの徹底が不可欠です。
メンタルヘルス対策と心理的安全性
ストレスチェックの実施と結果活用、ハラスメント防止措置、相談しやすい職場風土の醸成が求められます。
労働時間管理の徹底
客観的な労働時間の把握と、長時間労働の是正は、過労死・過労自殺を防ぐための基本的な責務です。
「命のプロ」が、企業の未来を守ります。
元陸上自衛隊幹部自衛官・社会保険労務士の渡辺 忍が、現場経験と専門知識を融合させ、貴社の「安全・安心」な職場づくりを実践的に支援します。
約1時間の診断で、貴社の潜在リスクを可視化します。