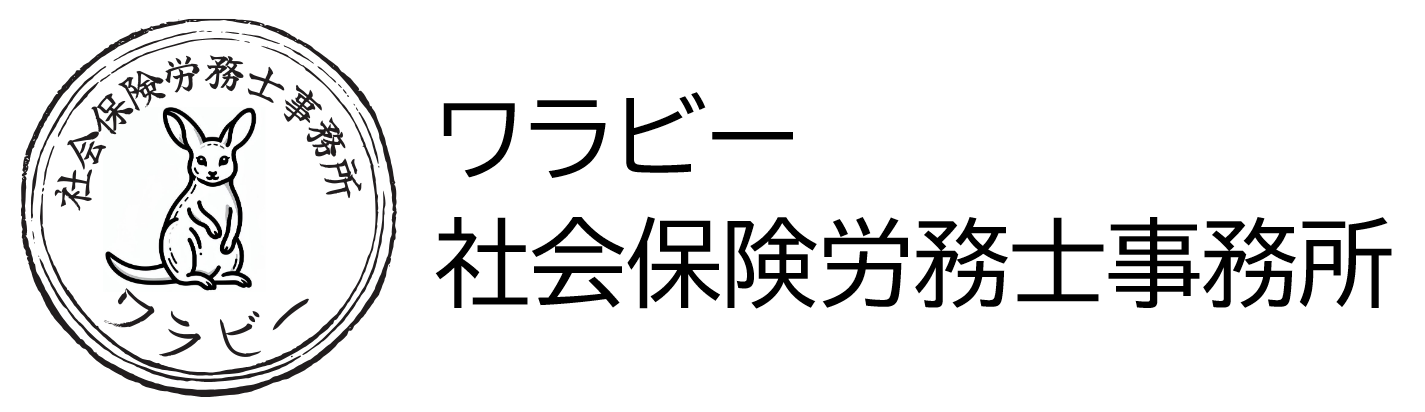職位に応じた「マネジメントの型」を持つことの重要性
はじめに
皆さん、こんにちは。私は陸上自衛隊の幹部自衛官として33年努めて退職し、現在は社会保険労務士として活動しています。30年以上の自衛隊生活で培った組織マネジメントと安全管理の知見をもとに、組織運営における重要な視点をお伝えしたいと思います。
年度替わりの3月から4月にかけては、多くの組織で人事異動の季節です。新たな役職、新たな職場で責任を担うことになる方も多いでしょう。そんな方々に向けて、自衛隊での経験から得た「マネジメントの型」の重要性について綴ってみたいと思います。
自衛隊での経験と「マネジメントの型」
自衛隊の幹部にとって、部隊指揮官という立場は花形のポジションです。しかし、30年以上の自衛隊キャリアを通じて、実際に指揮官として過ごす期間はほんの一部に過ぎません。私の場合、指揮官を務めたのは3回、期間にして6〜7年程度でした。残りの期間は一般のパイロットや幕僚、学校教官、あるいは「長」という肩書きを持つ幕僚(民間企業でいえば課長や係長に相当する中間管理職)として勤務していました。
これらの異なる立場を経験する中で痛感したのは、それぞれの職位には適した「マネジメントの型」が存在するということです。そしてこの「型」の違いを理解せず、職位が変わっても同じマネジメント手法を続けてしまうと、組織の機能不全を招くことがあるのです。
指揮官の「情報集約型」マネジメント
部隊指揮官のマネジメントスタイルは、典型的な「情報集約型」です。有事の際には、あらゆる情報を部下から適時適切に収集し、状況(いわゆる「戦機」)を的確に判断して、部隊の能力を最大限に発揮するための「決心」を下さなければなりません。
指揮官は部隊の最高責任者として、最終的な判断を下す役割を担います。そのため、部下には常に適切な情報を上げてくるよう求め、訓練します。指揮官の決断が部隊全体の命運を左右するため、この情報集約型のマネジメントは極めて合理的なのです。
指揮官は常に「決断する人」であり、その決断の質を高めるために情報を集める人でもあります。そのため、仕事の細部については部下に委ねることが多く、「大きな方針を示し、細部は任せる」というスタイルが基本となります。
この役割を理解している指揮官は、部下からの報告や提案を常に求め、「私の決心のために必要な情報を上げてくれ」という姿勢で組織を率います。その結果、部下たちも「指揮官の決心に資する情報を集め、整理して上げる」という役割を明確に認識し、組織全体が一つの目的に向かって機能するのです。
「長」がつく幕僚の「伴走型」マネジメント
一方、「長」という肩書きを持つ幕僚(課長や係長に相当する中間管理職)の役割は大きく異なります。彼らの理想的なマネジメントスタイルは「伴走型」です。
「長」がつく幕僚の主な役割は、指揮官が適切な「決心」を行えるように、部下を指導し、自らも部下と共に業務を遂行することです。指揮官のような最終決定権はなく、むしろ指揮官と部下をつなぐ調整役として機能します。
自衛隊の組織構造では、「長」がつく幕僚が隷下の部隊長よりも階級が高い場合があります。こうした状況で問題が生じやすいのは、階級の高さから権限を勘違いし、指揮官のような「決心」を下そうとする幕僚です。特に、以前指揮官を務めていた者が「長」がつく幕僚のポジションに異動してきた直後によく見られる現象です。
このような状況下では、部下は二人の「指揮官」に仕えることになり、混乱が生じます。「長」がつく幕僚の指示に従って仕事をしても、最終的に指揮官の意向と合わなければ覆されてしまうからです。これは部下にとって大きなストレスとなり、心理的安全性を著しく損ねることになります。
職位に応じたマネジメントスタイルの転換
私自身、指揮官から「長」がつく幕僚のポジションに異動した際、この転換の難しさを身をもって経験しました。指揮官として「決心」を下すことに慣れていた私は、最初のうち、知らず知らずのうちに幕僚としての立場でも「決心」を下そうとしていました。
しかし、それが部下たちの混乱を招き、指揮官との間で軋轢を生んでいることに気づいたのです。幕僚としての私の役割は、指揮官の「決心」をサポートし、部下たちがその「決心」に基づいて効率的に動けるよう導くことでした。
この気づきから、私は自分のマネジメントスタイルを「情報集約型」から「伴走型」へと意識的に転換しました。部下に対して「私はこうすべきだと思う」と指示するのではなく、「指揮官はこのような決心をされるだろうから、我々はこのような準備をしておこう」というアプローチに変えたのです。
その結果、部下たちの混乱は次第に解消され、組織全体の心理的安全性が高まっていきました。指揮官も私の役割変化を好意的に受け止め、より円滑な意思決定プロセスが確立されていったのです。
「状況の特質」を把握し最適な「マネジメントの型」を選ぶ
3月から4月にかけて、多くの方が新たな職場や役職に就くことになるでしょう。そこで重要なのは、自衛隊でいうところの「状況の特質」、つまり異動先の部署の業務内容、環境、人間関係などを速やかに把握することです。
民間企業であれば、事業部長、部長、課長といった役職によって求められるマネジメントスタイルは異なります。またプロジェクトリーダーとライン管理職では、必要なアプローチも変わってきます。
自分の職位や役割に応じた「マネジメントの型」を早期に確立することで、部下の混乱を最小限に抑え、組織の心理的安全性を確保することができます。これは組織のパフォーマンスを最大化する上でも極めて重要なポイントです。
心理的安全性の重要性
最後に強調したいのは、心理的安全性の重要性です。部下が安心して意見を述べ、失敗を恐れずに挑戦できる環境は、組織の創造性と生産性を高める基盤となります。
マネジメントの型が組織の役割や状況とミスマッチを起こすと、部下は「何を求められているのか」「誰の指示に従えばよいのか」という混乱に陥り、心理的安全性が損なわれます。特に「長」がつく幕僚が指揮官のような振る舞いをする場合、部下は板挟みとなり、萎縮してしまいます。
異動したばかりの管理職の方々には、自分が今いる立場で求められている役割を冷静に分析し、適切なマネジメントスタイルを選択していただきたいと思います。それが部下の信頼を勝ち取り、組織全体のパフォーマンスを向上させる第一歩となるのです。
おわりに
自衛隊での経験を振り返ると、職位に応じたマネジメントスタイルの転換がいかに重要かを実感します。組織の長たるもの、組織ごとの「マネジメントの型」を持ち、状況に応じて柔軟に変化させる能力が求められるのです。
新年度を迎える3月から4月、新たな挑戦を始める管理職の皆さんが、職場の「状況の特質」を速やかに把握し、最適な「マネジメントの型」を確立されることを心より願っています。それが心理的安全性の高い、生産性の高い職場づくりの第一歩となるはずです。