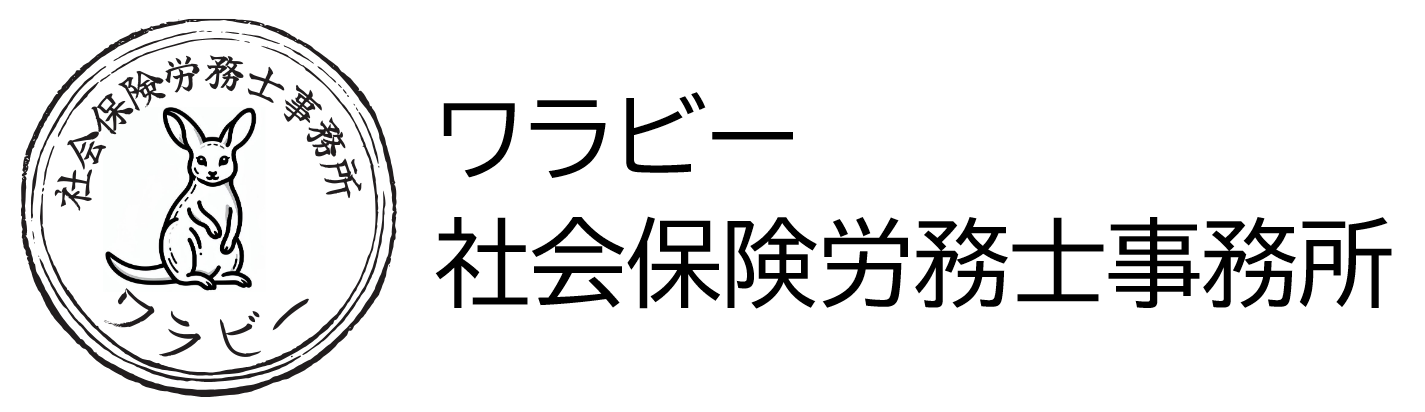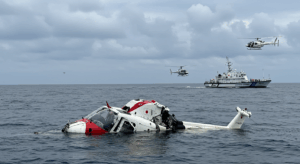令和7年4月・10月施行!育児介護休業法改正と就業規則改定の重要性
皆様、こんにちは。ワラビー社会保険労務士事務所代表の渡辺です。
令和7年(2025年)4月と10月に、育児介護休業法をはじめとした労働関連法規の改正が段階的に施行されます。これらの法改正は、企業の就業規則に直接的な影響を与え、適切な改定・メンテナンスが不可欠となります。
本稿では、これらの改正の主要なポイント、就業規則に具体的にどのような変更が必要となるのか、そして法改正に対応しない場合のリスクと、最新の法令に対応することのメリットについて詳しく解説します。就業規則の改定は専門的な知識を要するため、社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
今回の法改正は、仕事と育児・介護の両立支援を一層強化するものであり、企業はこれらの変更に適切に対応することで、従業員が安心して働き続けられる環境を整備することが求められます。法改正の内容を理解し、自社の就業規則を見直すことは、法令遵守だけでなく、従業員の満足度向上や企業イメージの向上にも繋がります。段階的な施行スケジュールを踏まえ、早めの準備と対応が重要となります。
令和7年4月施行の育児介護休業法改正:企業が対応すべき主要ポイント
令和7年4月1日から施行される育児介護休業法の改正では、育児期の働き方の柔軟性を高めるための措置が拡充されます。
まず、「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」へと名称が変更され、対象となる子の年齢が小学校就学前までから小学校3年生の修了前まで(9歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に拡大されます。また、休暇の取得理由も、従来の病気や怪我、予防接種、健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖や入園式、卒園式への参加も含まれるようになります。さらに、これまで労使協定により、雇用期間が6か月未満の労働者を子の看護休暇の取得対象から除外することが可能でしたが、この規定は撤廃されます。これにより、入社後間もない従業員であっても、子どもの看護等が必要な場合に休暇を取得できるようになります。
この改正により、これまで以上に幅広い状況で従業員が休暇を取得しやすくなるため、企業は就業規則において、これらの変更を反映する必要があります。特に、学級閉鎖や学校行事への参加が休暇理由として追加されたことは、子育て世代の従業員にとって大きな支援となり、より安心して働くことができる環境整備に繋がります。また、勤続期間による制限がなくなることで、より多くの従業員がこの休暇を利用できるようになるため、制度の周知徹底も重要となります。
次に、所定外労働の制限(残業免除)の対象となる子の年齢が、これまでの3歳未満から小学校就学前までに拡大されます。これにより、より長い期間にわたり、子育て中の従業員が残業を免除される可能性が広がります。
この変更は、育児期の従業員のワークライフバランスを支援する上で重要なポイントとなります。小学校入学前の子どもを持つ従業員は、依然として育児の負担が大きいことが想定されるため、残業免除の対象年齢が引き上げられることで、仕事と育児の両立がより一層支援されることになります。企業は就業規則において、この対象年齢の変更を明確に記載する必要があります。
また、3歳未満の子を養育する労働者の短時間勤務制度について、その代替措置として、従来の育児休業に関する制度に準ずる措置や始業時刻の変更等に加え、テレワークが追加されます。これにより、短時間勤務制度を導入することが難しい業務に従事する労働者に対しても、テレワークという柔軟な働き方を提供することが可能になります。
さらに、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主は措置を講ずる努力義務が課せられます。これは、企業がテレワークを育児支援の選択肢の一つとして積極的に検討し、導入を促進することが求められるという点で、重要な変更と言えます。
従業員数300人を超える企業については、育児休業等の取得状況の公表義務の対象が拡大されます。これまで公表義務があったのは従業員数1000人超の企業でしたが、改正後はより多くの企業が対象となります。公表する内容は、男性の育児休業等の取得率、または育児休業等と育児目的休暇の取得率です。
この義務拡大は、男性の育児休業取得を促進し、仕事と育児の両立支援に向けた企業の取り組みを可視化することを目的としています。対象となる企業は、就業規則に公表に関する規定を盛り込むとともに、取得状況を適切に把握し、公表する準備を進める必要があります。
介護休暇を取得できる労働者の要件も緩和されます。これまで、週の所定労働日数が2日以下であることと、継続雇用期間が6か月未満であることが、労使協定により介護休暇の取得対象外となる条件でしたが、このうち後者の継続雇用期間に関する要件が撤廃されます。これにより、入社後6か月未満の労働者であっても、介護が必要な家族がいる場合には介護休暇を取得できるようになります。
この変更は、介護離職の防止という観点から重要な意味を持ちます。雇用期間に関わらず、必要な時に介護休暇を取得できることは、従業員の安心感に繋がり、長期的な就労を支援する上で有効です。企業は就業規則において、この要件緩和を反映させる必要があります。
加えて、40歳に達した日の属する年度に、事業主は労働者に対して一定の介護に関する事項を知らせる義務が追加されます。これは、従業員が介護に直面する前に、介護休業や介護両立支援制度に関する情報を早期に提供し、準備を促すことを目的としています。
雇用保険法も改正され、子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」が創設されます。また、子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」も新たに設けられます。自己都合離職者の雇用保険の基本手当(失業給付)における原則の給付制限期間も、2か月から1か月に短縮されます。さらに、高年齢雇用継続給付については、最大給付率が各月に支払われた賃金額の15%から10%に引き下げられます。雇用保険の失業等給付に係る保険料率も0.1%引き下げられます。
これらの雇用保険法の改正は、従業員の育児休業取得や時短勤務を経済的に支援し、離職を防ぐとともに、再就職を促進する効果が期待されます。企業はこれらの制度変更について従業員に周知し、必要に応じて就業規則に反映させることも検討する必要があります。
次世代育成支援対策推進法も改正され、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、一般事業主行動計画の策定時において、「男性労働者の育児休業取得状況」および「労働時間の状況」を把握した上で、当該状況に関する数値目標を設定することが義務付けられます。
この改正は、男性の育児休業取得をさらに促進するためのものであり、企業は数値目標を設定し、その達成に向けて具体的な取り組みを進めることが求められます。就業規則においても、育児休業取得を奨励する方針や具体的な支援策を明記することが効果的です。
妊娠・出産等の申出があった場合、事業主は育児休業の制度などについて個別周知と意向確認を行うことが義務付けられていましたが、法改正により、これに加え、「仕事と育児の両立にかかる就業条件」について、個別の意向を聴取することが義務付けられます。
この義務は、従業員一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな支援を行うことを目的としています。企業は就業規則に、個別意向聴取の実施方法や配慮の内容などを定めることが望ましいでしょう。
令和7年10月施行の育児介護休業法改正:柔軟な働き方の実現に向けた新たな義務
令和7年10月1日からは、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対して、事業主が「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じることが義務付けられます。事業主は、以下の5つの制度の中から2つ以上を選択して導入する必要があり、労働者はその中から1つを選択して利用することができます。
- 始業時刻等の変更:フレックスタイム制、始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤)など。
- テレワーク等:1か月に10日以上利用できるテレワーク制度で、原則として時間単位での取得を可能とすることが求められます。
- 保育施設の設置運営等:事業所内保育施設の設置運営や、ベビーシッターの手配および費用負担など、これに準ずる便宜の供与。
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与:年間に10日以上取得できる休暇で、有給・無給は問いませんが、原則として時間単位での取得を可能とすることが求められます。
- 短時間勤務制度:1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置で、短縮分の賃金減額は可能です。
この義務化は、3歳から小学校就学前という、育児と仕事の両立が特に大変な時期にある従業員を支援するための重要な改正です。企業は、自社の状況や従業員のニーズを踏まえ、適切な措置を選択し、就業規則に明記する必要があります。また、これらの措置を導入するだけでなく、従業員が利用しやすいように周知徹底することも重要です。
事業主は、上記で選択した制度に関する以下の事項について、労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間において、個別に周知し、制度利用の意向を確認する義務があります。
- 事業主が選択した対象措置(2つ以上)の内容
- 対象措置の申出先(例:人事部など)
さらに、妊娠・出産等の申出時と、労働者の子が3歳になる前の時期の2回にわたり、事業主は以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません:
- 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
- 勤務地(就業の場所)
- 両立支援制度等の利用期間
- 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
そして、事業主は、これらの聴取した労働者の意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
これらの義務は、企業が従業員の育児状況や希望を丁寧に把握し、可能な範囲で柔軟な働き方を支援することを求めるものです。就業規則には、これらの個別周知や意向聴取、配慮に関する手続きや基準を明確に定めることが重要となります。
要介護状態の対象家族を介護する労働者に関し、事業者はテレワークを利用できる措置を講ずることが努力義務となります。
就業規則への具体的な反映:改正内容を踏まえた修正・追加条項の検討
今回の育児介護休業法改正に対応するため、企業は就業規則において以下の点を中心に修正や追加を検討する必要があります。
まず、子の看護休暇に関する条項については、「子の看護等休暇」への名称変更、対象年齢の小学校3年生修了前までの拡大、取得理由への感染症に伴う学級閉鎖や入園式・卒業式の追加を反映させる必要があります。また、勤続6か月未満の従業員を除外する規定がある場合は削除する必要があります。
次に、所定外労働の制限に関する条項では、対象となる子の年齢を小学校就学前までに修正します。
3歳未満の子を養育する従業員に対する短時間勤務制度の代替措置としてテレワークを導入する場合は、その条件や利用方法に関する条項を追加します。また、テレワーク導入を努力義務として規定する場合も、その旨を明記することが望ましいでしょう。
10月からの改正で義務化される柔軟な働き方を実現するための措置については、自社が選択する2つ以上の制度の内容、利用条件、申請方法などを具体的に定める条項を新設する必要があります。例えば、フレックスタイム制や時差出勤制度を導入する場合は、その運用ルールを詳細に規定し、養育両立支援休暇を付与する場合は、取得日数や取得単位、有給・無給の別などを明確にする必要があります。
介護休暇に関する条項では、勤続6か月未満の従業員を除外する規定を削除します。
従業員数300人を超える企業の場合は、男性の育児休業等の取得状況を年1回公表する義務に関する条項を追加する必要があります。
40歳に達した従業員等への介護に関する情報提供義務に関する条項や、妊娠・出産等を申し出た従業員や3歳になる前の従業員に対する仕事と育児の両立に関する意向聴取と配慮に関する条項を追加することも重要です。
以下は、就業規則の改定における主な修正・追加ポイントをまとめた表です。
| 法改正内容 | 就業規則の修正・追加ポイント |
| 子の看護休暇の名称変更と対象拡大 | 「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に変更、対象年齢を小学校3年生修了前までに拡大、取得理由に学級閉鎖や学校行事を追加 |
| 所定外労働の制限の対象拡大 | 対象となる子の年齢を小学校就学前までに拡大 |
| 育児短時間勤務の代替措置へのテレワーク追加 | 3歳未満の子を養育する従業員に対する短時間勤務が困難な場合の代替措置として、テレワークに関する規定を追加 |
| 育児のためのテレワーク導入の努力義務 | 3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを選択できるよう、事業主が措置を講ずる努力義務に関する規定を追加 |
| 育児休業取得状況の公表義務の拡大 | 従業員数300人超の企業は、男性の育児休業等の取得状況を年1回公表する義務に関する規定を追加 |
| 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 | 勤続6か月未満の従業員を除外する規定を削除 |
| 介護に関する事項の情報提供義務の追加 | 40歳に達した従業員等に対して、介護休業や介護両立支援制度に関する情報を提供する義務に関する規定を追加 |
| 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化 | 3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員に対し、選択する2つ以上の柔軟な働き方に関する制度(始業終業時刻の変更、テレワーク、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務)の内容、利用条件、申請方法などを具体的に定める条項を新設 |
| 個別周知・意向確認・意向聴取・配慮の義務化 | 柔軟な働き方に関する措置の個別周知・意向確認、妊娠・出産等の申出時と3歳になる前の従業員に対する仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮に関する手続きや基準を定める条項を追加 |
育児介護休業法以外の労働関連法改正:令和7年4月以降の注目すべき変更点
令和7年4月以降には、育児介護休業法以外にも、雇用保険法や次世代育成支援対策推進法など、労働関連の重要な法律が改正されます。
雇用保険法では、出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金が創設され、失業給付の給付制限期間が短縮されるなどの変更があります。また、高年齢雇用継続給付の給付率が引き下げられ、雇用保険料率も一部改定されます。これらの変更は、従業員の休業や再就職、高齢者の雇用継続などに影響を与えるため、企業は内容を正確に理解し、必要に応じて就業規則や労務管理体制を見直す必要があります。
次世代育成支援対策推進法では、従業員数101人以上の企業に対して、男性労働者の育児休業取得状況などに関する数値目標の設定が義務付けられます。これは、男性の育児参加を促進するための国の取り組みの一環であり、対象となる企業は、就業規則に育児休業取得を奨励する方針を明記するなど、具体的な対策を検討する必要があります。
就業規則を放置するリスク:法令違反、労務トラブル、企業イメージへの影響
法改正に対応しない就業規則を放置した場合、企業は様々なリスクを負う可能性があります。
まず、改正された法律に違反する状態となり、労働基準監督署からの是正勧告や指導を受ける可能性があります。法令違反の内容によっては、罰則が科されることもあります。
また、従業員との間で労務トラブルが発生する可能性も高まります。例えば、改正前の規定に基づいて育児休業や介護休暇の申請を拒否したり、旧来の条件で運用を続けたりした場合、従業員からの不満や訴訟に繋がる可能性があります。未払い賃金や不当解雇といった問題に発展するリスクも考えられます。
さらに、法改正に対応しない企業は、従業員からの信頼を失い、企業イメージを損なう可能性があります。特に、育児や介護といった従業員の生活に関わる重要な制度について、時代に合わせた適切な対応を怠ることは、従業員のモチベーション低下や離職に繋がりかねません。
助成金の申請においても、最新の法令に対応した就業規則の整備が要件となっている場合が多く、法改正に対応していない就業規則のままでは、助成金を受けられない可能性もあります。
最新法令に対応した就業規則を整備するメリット:従業員満足度向上、企業イメージ向上、助成金活用
最新の法令に対応した就業規則を整備することには、企業にとって多くのメリットがあります。
まず、従業員が安心して働ける環境を整備することができます。育児や介護といったライフイベントと仕事の両立を支援する制度が整っていることは、従業員の満足度向上に繋がり、優秀な人材の定着を促進します。柔軟な働き方が選択できることは、従業員のエンゲージメントを高め、生産性向上にも寄与します。
また、法改正に積極的に対応する企業は、社会的な評価が高まり、企業イメージの向上に繋がります。従業員を大切にする企業というイメージは、採用活動においても有利に働き、優秀な人材の獲得に繋がります。
さらに、最新の法令に対応した就業規則を整備することで、各種助成金の申請が可能になる場合があります。政府は、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む企業に対して様々な助成金を用意しており、これらの助成金を活用することで、制度導入や運営にかかるコストを軽減することができます。
就業規則の改定は専門家へ:社会保険労務士に相談するメリット
就業規則の改定は、専門的な知識と時間、労力を必要とする作業です。特に、今回の育児介護休業法をはじめとする労働関連法規の改正は多岐にわたり、その内容を正確に理解し、自社の就業規則に適切に反映させるためには、専門家のサポートが不可欠と言えます。
社会保険労務士は、労働法に関する専門知識と豊富な経験を持っており、最新の法改正情報にも常に精通しています。そのため、複雑な法改正の内容を分かりやすく解説し、企業の実情に合わせた最適な就業規則の改定案を提案することができます。
社会保険労務士に就業規則の作成や改定を依頼することで、法令遵守を確実にし、労務トラブルを未然に防ぐことができます。また、効率的に就業規則を作成・改定できるため、担当者の負担を軽減し、本来の業務に集中することができます。
さらに、社会保険労務士は、企業の特性や業界の慣行を踏まえた上で、オーダーメイドの就業規則を作成することができます。これにより、企業の成長や変化に対応できる、実効性の高い就業規則を整備することが可能になります。
助成金の申請についても、社会保険労務士は専門的な知識とノウハウを持っており、申請手続きのサポートや、助成金受給のための就業規則の整備に関するアドバイスを受けることができます。
就業規則の作成・変更は、社会保険労務士の独占業務と定められています。安心して就業規則の改定を進めるためには、社会保険労務士への相談が最も確実な方法と言えるでしょう。
まとめ:法改正に対応した就業規則で、持続可能な企業成長を
今回のブログでは、令和7年4月と10月に段階的に施行される育児介護休業法をはじめとした労働関連法規の改正の主要なポイントと、企業が就業規則を改定する際の注意点について解説しました。
法改正への対応は、単なる義務ではなく、従業員が安心して働き続けられる環境を整備し、企業の持続的な成長を支えるための重要な取り組みです。最新の法令に対応した就業規則を整備することで、法令違反のリスクを回避し、労務トラブルを未然に防ぐとともに、従業員満足度や企業イメージの向上、助成金の活用など、多くのメリットを享受することができます。
今回の法改正は、育児や介護を行う従業員にとって働きやすい環境を整備するための大きな一歩となります。企業はこの機会を捉え、就業規則の見直しを通じて、より良い職場環境づくりに取り組んでいただきたいと思います。
就業規則の改定は専門的な知識を必要としますので、ぜひこの機会にワラビー社会保険労務士事務所にご相談ください。オンラインにて貴社の状況を詳しくお伺いし、最新の法令に基づいた最適な就業規則の作成・改定をサポートさせていただきます。